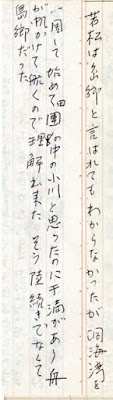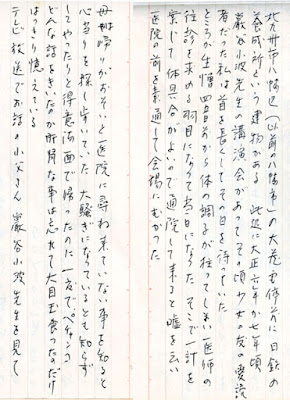舟山に登る
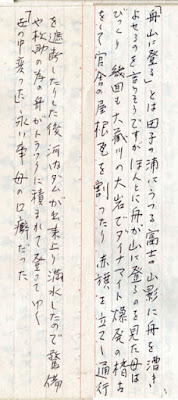
<1b-35-4> 「舟山に登る」とは田子の浦にうつる富士の山陰に 舟を漕ぎよせるのを言うそうですが ほんとに舟が山に登るのを見た母はびっくり 幾回も大蔵川の大岩でダイナマイト爆発の稽古をして 官舎の屋根瓦を割ったり 赤旗を立てゝ通行を遮断したりした後 河内ダムが出来上がり 満水したので警備や救助の為の舟がトラックに積まれて登ってゆく 「 世の中変わった 」 永い事母の口癖だった 《わたしのメモ》 北九州市八幡東区にある河内ダムは八幡製鉄所(現新日鉄住金)のダムで1919年(大正8年)に着工、1927年(昭和2年)に完工しています。 製鉄所の大蔵の官舎に住んでいたので、工事の様子をよく見ていたのでしょう。 ダムの下流は大蔵を通りますが、板櫃川(いたびつがわ)となっています。 しかし別名「大蔵川」とも言うようです。 「舟山に登る」は 一般的な故事諺の「船頭多くして船山に登る」と思いますが ここでは違うようです。 それにしても当時の大工事だった様子がわかります。 下の写真は1971年8月頃の河内ダム。 石造りのダムが綺麗です。