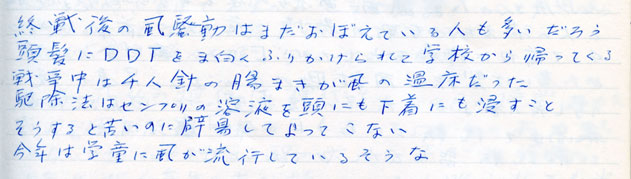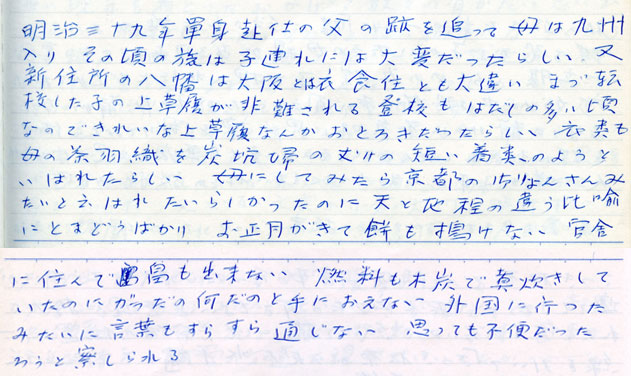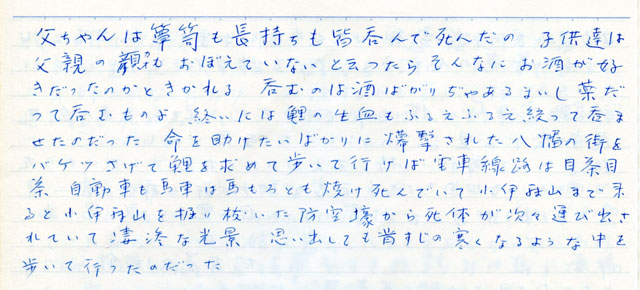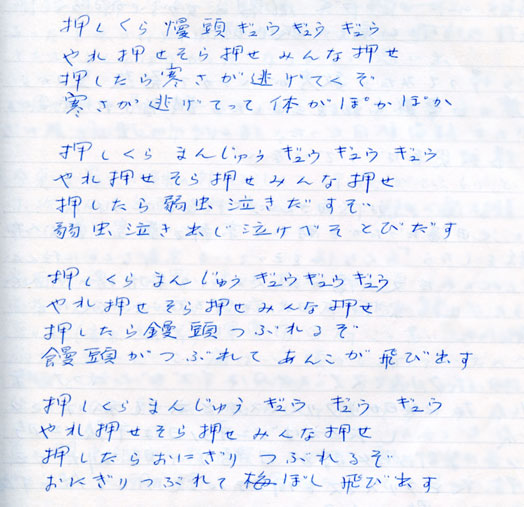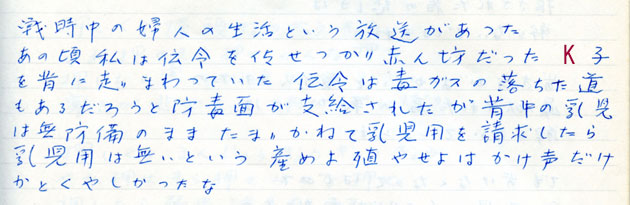小学校の担任の先生

<4-52-1> 入江スガノ先生には小1,2,3年の3年間お世話になった やさしいとても好きな先生が病気で退職されるときき 電車で先生のお宅まで見舞いに行ったらとても嬉んでくださって涙を流して下さった よくも大胆にあんな遠くまで行ったもの <4-52-2> 小4の担任は神代先生 4月の授業開始の日 開口一番「4年生にもなって5年生の本が読めないのか」と飛上る程の大きな声で叱られた 5年生が4年生の本が読めないなら叱られても当り前だが キョトンとしていた それから前日に家庭でよーく読んでおいて学校では不審な所を聞くことした 老令の為 男子中学(今の高校)をやめて小学校教師となった一風変った方だった とてもいい先生だった 《凡人の雑感》 電車でお見舞いって 小学生がどこまで見舞いに行ったのですかね。 子供の頃から実行力があったようです。 それにしても小学校の事をよく憶えています。 私が憶えているのは 小学校に入学した時は女の先生で大谷先生。 「やさしい先生」だったと記憶しています。 何しろ入学時には泣きべそ小僧だった私には、天使のような先生だったと思っています。 亡母もこの先生の事は、ずっと「良い先生」だったと云ってました。 5・6年の担任は男の先生で相原先生。 大変おせわになった先生です。 亡母にもこの先生はやっぱり「よい先生」だったようです。 この先生が園芸部の先生だったので私も所属していました。 また夏休みにはクラスで希望する5・6人ほどを、あがの峡や千石峡、中学になってからも耶馬渓などにキャンプに連れて行ってもらってました。 その時の体験から、その後キャンプや山登りが好きになり、歳をとった今でも近くの山を彷徨しています。 ところで 二年生から四年生までの記憶がほとんどないのは…ボーッとした性格だったからでしょうか? それともそろそろ私にも老人特有の症状が………(>_<) さらに その間の写真さえも残っていません。 そうです、そうです 写真が無いから記憶を呼び戻せないのかも知れませんね。 目出度し めでたし (^^ゞ